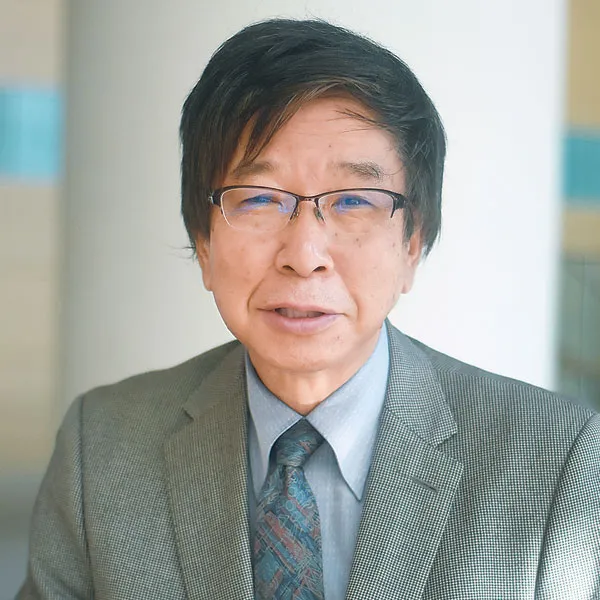2025-11-13 コメント投稿する ▼
立憲民主党逢坂誠二氏が物価高で政策転換訴え、海員組合大会で格差拡大に警鐘
全日本海員組合第86回大会で立憲民主党の逢坂誠二氏が政策転換訴え 物価高騰で家計圧迫、海事産業の人手不足も深刻化。 2025年11月12日から13日の両日、鹿児島県内で開催された全日本海員組合第86回定期全国大会で、同組合の政治参与でもある立憲民主党の逢坂誠二衆院議員が党を代表して出席し、現在の経済政策の根本的な転換を訴えました。
2025年11月12日から13日の両日、鹿児島県内で開催された全日本海員組合第86回定期全国大会で、同組合の政治参与でもある立憲民主党の逢坂誠二衆院議員が党を代表して出席し、現在の経済政策の根本的な転換を訴えました。
経済指標と生活実感の深刻な乖離
逢坂誠二氏は祝辞の中で、日本経済の表面的な好調さと実際の国民生活の困窮状況について鋭く指摘しました。株価が5万円を超え、企業の内部留保が600兆円を超えるなど数字上は好景気に見える一方で、生活保護申請件数の増加や物価・電気料金の上昇により家計が圧迫されている現実を浮き彫りにしました。
この深刻な格差拡大について、逢坂氏は「数字上の景気回復と生活実感の乖離」が広がっていると警鐘を鳴らし、政治の役割として「国民の命と暮らしを守ることが最優先」だと強調しました。物価高対策として、現在の数十年に渡る自民党政権の経済政策が招いた危機的状況に対し、一刻の猶予も許されない財政出動や減税が必要だと訴えました。
「株価は上がってるけど、うちの生活は全然楽にならない」
「電気代も食費もどんどん高くなって、もう限界です」
「企業は儲かってるのに、なんで給料は上がらないの」
「政治家の人たちは庶民の暮らしをわかってない」
「減税してくれないと、もう生活できません」
海事産業を取り巻く厳しい現実
全日本海員組合の松浦満晴組合長氏は、鹿児島県が全国一の離島数を有し、海運・水産業の重要拠点である特性を踏まえながら、海事産業が直面する深刻な課題について言及しました。
特に、労働条件や賃金の改善が進まず、後継者不足が深刻化している現状を問題視し、「厳しい労働環境のままでは次の世代が働く意欲を持てない」と述べました。離島住民の暮らしと日本の物流を支える船舶・船員の重要性を強調し、「国の政策は現場の実情を踏まえ、逆行してはならない」と政策転換を求めました。
海事産業では2025年問題により人手不足がさらに深刻化することが予想されています。物流業界全体で労働時間の上限規制により運送能力が低下する中、海上輸送の重要性はますます高まっています。しかし、海員の労働環境改善が追いつかず、若者の海事産業離れが加速している状況です。
脱炭素化への取り組みと課題
松浦組合長は、持続可能な海洋産業の発展に向けた取り組みの重要性にも触れ、燃料転換や自動運航技術の導入など、技術革新の加速を求めました。海運業界では脱炭素化が急務となっており、国際海事機関による2050年カーボンニュートラル目標達成に向けた具体的な施策が求められています。
しかし、新技術導入には多額の投資が必要で、中小海運事業者の経営を圧迫する可能性があります。政府による技術開発支援や設備投資への補助制度の充実が不可欠な状況です。
立憲民主党の政策方針
逢坂氏は最後に、立憲民主党の基本姿勢として「海で働く人々をはじめ、すべての働く人の命と暮らしを守るため、全力で取り組む」と決意を表明しました。これは、従来の大企業優遇政策から、働く人々の生活を重視する政策への転換を意味しています。
全日本海員組合は1945年10月設立の日本で唯一の海事関連産業別単一労働組合で、現在約2万人の組合員と外国人船員を含め約4万人が加入しています。鹿児島県は離島面積・人口ともに全国1位を誇り、28の有人離島を抱える海洋県として海運業の発展は地域経済にとって極めて重要な位置を占めています。