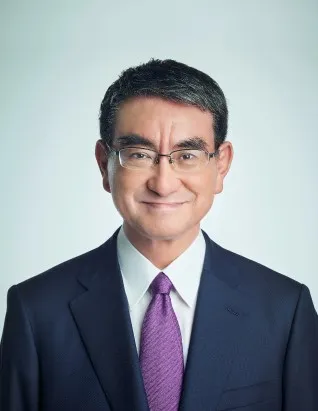2025-08-14 コメント投稿する ▼
茨城県、将来の必要外国人労働者は最大50万人 ベトナムなどから受け入れ拡大へ
茨城県、将来の必要外国人労働者は最大50万人 受け入れ体制整備へ
茨城県議会は7月30日、第5回「未来を拓く新たな茨城づくり調査特別委員会」を開催し、外国人労働者の受け入れ現状と課題について議論した。会合には独立行政法人教職員支援機構や関彰商事株式会社などが招かれ、県内産業界における人材不足の実態と外国人材活用の方向性について説明が行われた。
将来推計、最大50万人の外国人労働者が必要
説明によると、茨城県の労働力人口は減少傾向が続き、2050年には全産業で約27万5,000人が不足する見通しだ。この不足を補うには、外国人労働者の数を大幅に増やす必要があるとされ、2050年時点で必要な外国人労働者数は20〜30万人、在留期間や帰国率を考慮すると40〜50万人に達すると試算されている。
2024年10月末時点で県内に在留する外国人労働者は6万1,909人。国籍別ではベトナム(25%)、中国(13%)、インドネシア(14%)、フィリピン(12%)、ブラジル(7%)、その他(29%)となっており、アジア圏出身者が過半を占める。
「これからの茨城は外国人抜きでは成り立たない」
「数字だけ見ると急激な依存度上昇が心配」
生活・就労支援の拡充
県は、外国人が住みやすい環境づくりの一環として、多言語による相談体制の充実や生活支援を強化する方針を示した。特に日本語に不慣れな外国人でも安心して働ける環境を整えるため、母語対応の相談窓口を拡充する。
医療分野では、日本語が不自由な外国人患者も日本人と同等の医療サービスを受けられるよう、医療機関や薬局向けに多言語遠隔医療通訳サービスを提供している。
「言葉の壁をなくさないと、生活も就労も安定しない」
免許取得や運転免許切替の利便性向上
交通分野では、外国人の免許取得支援として、通常の運転免許学科試験を20言語で実施。外国免許からの切替については、待機日数の短縮や利便性向上を目的に職員増員で処理能力を強化している。さらに、オンライン予約や通訳システム導入も進め、申請の効率化を図っている。
「免許取得や切替のハードルを下げるのは大きな助けになる」
「交通ルールの理解不足による事故増加には注意が必要」
課題と今後の焦点
外国人労働者の増加は、労働力不足を補う重要な施策とされる一方で、急激な受け入れ拡大による地域社会の変化や治安、教育、医療の負担増を懸念する声もある。特に最大50万人規模という試算は、県の総人口比で見ても大きく、地域の文化や生活環境に与える影響は無視できない。
「受け入れるだけでなく、文化や法律の順守を徹底してほしい」
「国や県の方針が現場任せにならないようにしてほしい」