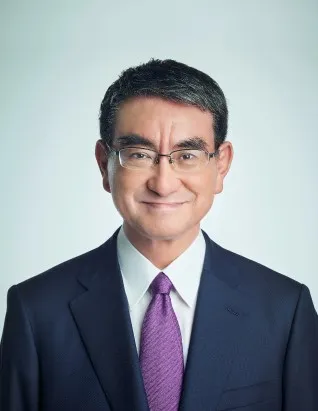2025-08-06 コメント投稿する ▼
神奈川県が多文化共生セミナー開催へ 外国人介護からイスラム文化まで学ぶ2回シリーズ
神奈川県、多文化共生セミナーを9・10月に開催
神奈川県は、異なる文化や背景を持つ人々が共に暮らす地域社会のあり方を探るため、9月と10月に多文化共生セミナーを開催する。主催は公益財団法人かながわ国際交流財団で、少子高齢化や外国籍住民の増加を背景に、受け入れ側である日本人が知っておくべき視点や配慮を学ぶ機会と位置づけられている。
黒岩祐治知事は、県政の重点施策の一つに多文化共生を掲げており、今回のセミナーもその取り組みの一環。外国籍住民が地域社会で主体的な役割を担えるよう、相互理解を深めることが狙いだ。
9月は外国人介護ワーカーの現状に焦点
9月23日に行われる第1回セミナーのテーマは「日本の福祉を共に支える外国人介護ワーカーの今」。少子高齢化が進む日本では、介護現場で外国人労働者の存在が欠かせなくなっている。セミナーでは、講師が取材で得た現場の状況をもとに、受け入れ体制や地域住民との関わり方を考える。
「外国人スタッフのおかげで介護現場が回っている」
「言葉や文化の違いをどう乗り越えるかが鍵」
「地域の理解がなければ長く働けない」
10月はイスラム文化と地域共生を学ぶ
10月20日の第2回セミナーは「実は身近なイスラムの暮らし:地域のモスクから考える共生のヒント」。日本国内には170以上のモスクがあり、地域との交流や相互理解の拠点となっている。講師はイスラム教の基礎知識や日本におけるモスクの役割を解説し、文化や宗教への理解を通じて地域共生のヒントを探る。
「モスクは宗教施設であると同時に地域交流の場」
「イスラム文化を知ることで誤解や偏見は減る」
「共生には知識と相互尊重が欠かせない」
多文化共生の課題と展望
神奈川県は全国有数の外国籍住民が多い地域であり、文化や宗教の違いを受け入れることが地域の活力にもつながる。一方で、制度や習慣の違いから摩擦が生じる場面も少なくない。今回のセミナーは、単なる情報提供ではなく、参加者が自身の地域でどのように関わるべきかを考えるきっかけとなることが期待される。
多文化共生は行政だけでなく、地域住民一人ひとりの理解と行動に支えられる。外国人が日本社会に適応し、日本人も異文化を理解する「双方向の努力」が求められている。