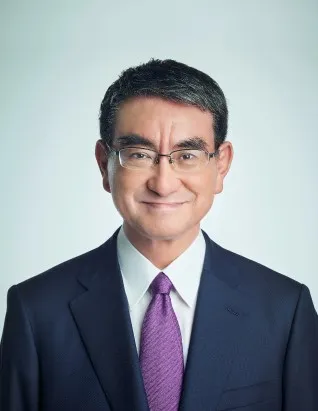2025-08-13 コメント投稿する ▼
公約沖縄の子牛生産が赤字経営に追い込まれる 高騰する飼育コストと補填制度の壁
沖縄の子牛生産、深刻な赤字経営
沖縄県内の子牛生産農家がかつてない経営難に直面している。近年の物価高騰で、1頭を出荷するまでにかかるコストは80万円を超える一方、セリでの取引価格は50万円前後と大幅に下回っている。差額は農家の持ち出しとなり、赤字が常態化している状況だ。
国や県は、セリ価格が一定基準を下回った際に差額を補填する制度を設けているが、今年4月以降はわずかに基準を上回ったため対象外となった。基準とのわずかな差で支援を受けられず、農家の間では制度の柔軟化を求める声が高まっている。
「今のままでは来年まで持たない」
「赤字で飼い続けるのは限界」
「県はもっと即効性のある支援を」
「飼料も資材も値上がり続けている」
「補填制度が基準一点で切り捨てるのはおかしい」
生産コスト高騰の背景
子牛生産にかかる費用の中で大きな割合を占めるのが飼料費だ。世界的な穀物価格の上昇や円安の影響で、輸入飼料の価格は数年前に比べ大幅に上昇。さらに電気代や燃料費も高止まりし、畜舎の維持費や運搬費も農家の負担を押し上げている。
また、沖縄は島嶼地域という特性から輸送コストが本土より高く、資材や機材の調達にも割高感がある。こうした構造的要因も、県内農家の経営を厳しくしている。
支援制度の限界
現行の補填制度は全国一律の基準を採用しており、基準額を1円でも上回れば補填対象から外れる仕組みだ。農家側からは「地域の実情やコスト構造を反映していない」との批判がある。特に沖縄のように輸送費や資材費が高い地域では、現行制度が経営実態に合っていないとの指摘が相次いでいる。
農家からの要望
農家からは、即効性のある資金支援に加え、補填制度の見直しや地域別基準の導入を求める声が強い。コスト削減や効率化の取り組みも進められているが、限界があり、制度的な支えがなければ廃業に追い込まれる農家が出かねない状況だ。
県内畜産業は、黒毛和牛の繁殖などブランド価値の高い産業として地域経済を支えてきた。だが、この危機が長引けば産業基盤そのものが揺らぎかねず、県経済にも深刻な影響を及ぼすことは避けられない。
この投稿は玉城デニーの公約「畜産物、サトウキビ、野菜、果樹、花き、水産物などの農林水産物の付加価値を高めるために、生産、加工、流通の一体的な振興を図ります。」に関連する活動情報です。この公約は0点の得点で、公約偏差値31.2、達成率は0%と評価されています。