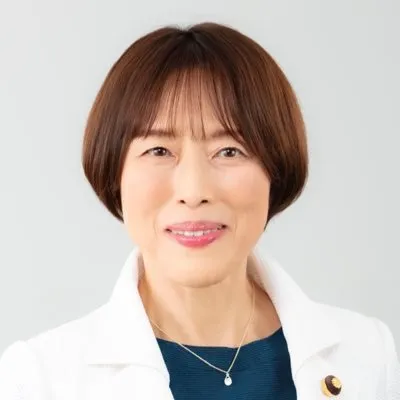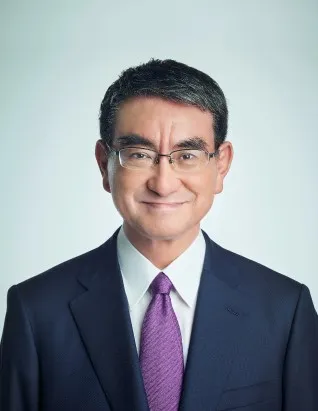2025-08-25 コメント投稿する ▼
種子法廃止と種苗法改正の影響 自家増殖禁止が農家と食の未来に与える危機
種子法廃止と種苗法改正が投げかける問題
日本の食料政策をめぐって大きな議論を呼んでいるのが、2017年に廃止された種子法と、2022年に改正施行された種苗法である。うつみさとる氏(参院神奈川選挙区候補)はSNSで「種子法と種苗法が日本を滅亡に向かわせている」と警鐘を鳴らし、農業と食のあり方を根本から揺るがすと訴えている。
もともと種子法は、国民が米や麦、大豆などの主要農産物を安価で安定的に入手できるよう、国と自治体が公共的に種子を管理・供給する仕組みを定めていた。しかし2017年4月に廃止され、公共の管理から民間企業主導の市場へと移行した。これによって、農家が安価に良質な種子を入手できる体制が揺らぎ、食料安全保障への懸念が高まった。
種苗法改正の核心は「自家増殖禁止」
さらに問題視されているのが、2022年4月から施行された種苗法の改正である。今回の改正で大きく変わったのは、①栽培地域の指定、②自家増殖の許諾の2点だ。特に注目されるのは、自家増殖、すなわち農家が自ら収穫した種や苗を翌年以降も利用する行為が、原則として禁止された点である。
農林水産省は「影響を受ける品種は少なく、許諾料の割合も低い」と説明するが、実際には登録品種の多くが対象となり、農家は毎年、種苗会社や権利者から新しい種を購入せざるを得なくなる。伝統的に農家が行ってきた「自給的な循環」は断ち切られ、経済的な負担が増すとの指摘が相次いでいる。
「農家から自家採種を奪うのは伝統を壊すことだ」
「結局、大企業や外国企業の利益になる仕組みだ」
「農家が安心して続けられなくなれば地域が衰退する」
「食料安全保障を軽視した法改正だと思う」
「種を買わされ続ける仕組みは食の独立を失わせる」
食の支配と外国企業の影
懸念されるのは、国内農業が外国企業の支配下に置かれる可能性である。登録品種の独占的販売権が守られる一方で、実際に市場で強い影響力を持つのは巨大資本を背景にした海外の種子企業である。農家は国産の伝統品種よりも、企業が供給する特定の種苗を購入し続けるよう誘導されかねない。これは「食の支配」に直結し、国民の食卓が外資依存に傾く危険性をはらんでいる。
さらに、種苗法改正の建前として「海外流出防止」が挙げられるが、実態としては農家の自立的な営農を制限し、企業依存を進める側面が強い。もし国内農家が外国企業の提供する種苗を毎年購入し続ける構図が定着すれば、農家の利益は圧迫され、農業そのものが持続困難になりかねない。
農業と国の未来に問われる政策転換
食料は国の基盤であり、主権の一部でもある。種子法廃止と種苗法改正によって、日本の農業が外資や大企業に依存する方向へ進めば、国民が望む「安全で安価な食」を守れなくなる危険がある。農家が自らの畑で採種した種を自由に使えない状況は、農業文化の喪失でもある。
いま必要なのは、農家の権利を守りつつ、海外流出のリスクに対応できる仕組みを再構築することだ。国が公共的役割を放棄するのではなく、食料主権を守る視点で政策を立て直さなければならない。うつみ氏が訴えるように、この問題は単なる法律論にとどまらず、日本の将来を左右する国家的課題となっている。