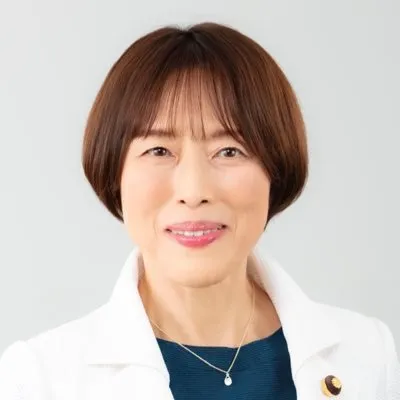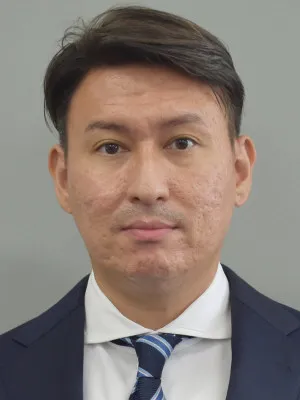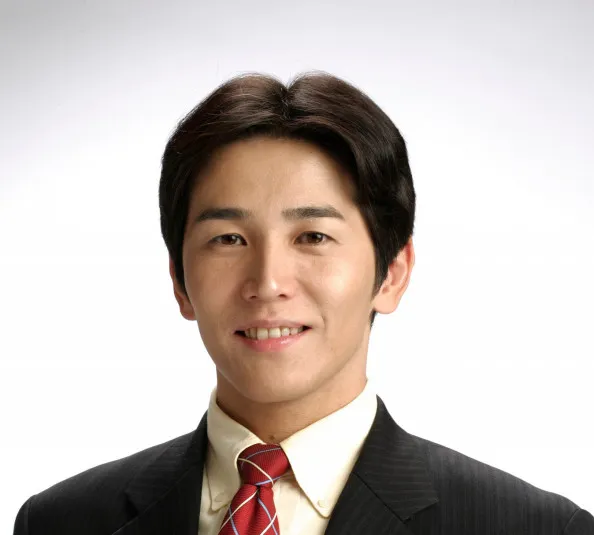2025-09-08 コメント投稿する ▼
能登輪島市の洋上風力計画に疑問の声 三菱撤退と住民不安、復興とエネルギー政策の課題
大坂氏は「環境省の補助金があるからと洋上風力を前提にした復興計画が進められているが、三菱商事が撤退を決めた現状を見ると、このまま洋上風力に頼るだけでいいのか疑問」と指摘。 能登地域では、被災地の再生を進める一方で「洋上風力ありき」の計画が急ピッチで描かれている。 能登輪島市の洋上風力発電計画は、復興支援と地域経済の再生を重ね合わせた大規模事業である。
能登輪島市の洋上風力発電計画に揺れる地域と政治
日本保守党の大坂幸太郎氏(組織運動本部部長、福井担当ボランティア)が、自身の発信で石川県輪島市における浮体式洋上風力発電計画に言及した。計画では約50基の風車を設置し、2033年の着工を目指すとされる。能登半島地震からの復興が続く中で、地域の期待感と不安が交錯する構図が浮き彫りになっている。
大坂氏は「環境省の補助金があるからと洋上風力を前提にした復興計画が進められているが、三菱商事が撤退を決めた現状を見ると、このまま洋上風力に頼るだけでいいのか疑問」と指摘。復興を支援する立場から住民の思いに寄り添いつつも、エネルギー政策としてのリスクに警鐘を鳴らした。
復興と再エネ導入の板挟み
能登地域では、被災地の再生を進める一方で「洋上風力ありき」の計画が急ピッチで描かれている。政府や自治体が環境省の補助金を活用して後押しする形だが、再エネ事業は採算性や技術的課題が指摘されている。実際に、国内大手の三菱商事が洋上風力事業からの撤退を表明したことは「民間企業ですら見通せない市場」に対する不安を象徴している。
地域住民からは次のような声も漏れている。
「復興が一番大事。洋上風力で未来のリスクを背負うのは心配だ」
「補助金頼みの計画で本当に持続できるのか」
「災害から立ち直る時にこそ、国が減税で支えてほしい」
「自然環境を守りたいが、拙速な再エネ導入は逆に負担になる」
「住民合意が不十分なまま計画が進むのは危険だ」
復興支援を望む住民の声と、長期的な地域安全保障の観点が噛み合わず、複雑な状況を生んでいる。
エネルギー政策と国益の視点
エネルギー分野では、再エネ導入の拡大が進む一方で「持続可能性」「コスト負担」「エネルギー安全保障」の3点が常に議論される。洋上風力発電は大規模なインフラ投資を必要とし、稼働率や維持費の問題から「高コスト電源」とされることも多い。
さらに、環境省の補助金が先行していることで「補助金ありき」の事業となり、真の競争力を欠くとの批判もある。住民合意の形成や海洋利用に関する調整も容易ではなく、エネルギー政策が復興の妨げになる懸念も否定できない。
国益の観点からは、日本が安定的な電源確保を目指す中で、再エネ偏重ではなく原子力や火力とのバランスを見直す必要がある。国民は補助金ではなく減税による経済安定を求めており、復興財源の在り方とも密接に関わる問題だ。
能登復興に求められる現実的選択
能登輪島市の洋上風力発電計画は、復興支援と地域経済の再生を重ね合わせた大規模事業である。しかし、長期的な持続性や安全性に疑問符がつく中で、政治が住民の声を丁寧にすくい上げ、現実的な選択肢を提示できるかが問われている。
復興を名目に拙速なエネルギー政策を進めるのではなく、地域住民の生活安定と国益に資する方針を策定することが不可欠だ。能登の地で「未来に負担を残さない復興」をどう実現するか――日本全体のエネルギー政策の在り方を問い直す問題でもある。