2025-08-18 コメント投稿する ▼
へずまりゅう氏「外国人生活保護は不要」発言に賛否 制度の矛盾と国民優先論を検証
へずまりゅう氏「外国人生活保護不要」発言が波紋
大阪市議のへずまりゅう氏が、外国人への生活保護をめぐり強い主張をSNSに投稿し、議論を呼んでいる。氏は次のように述べた。
生活が困難なら日本で悩まず母国に帰ればいいだけの話です。日本人が汗水流して納めた税金は国民の為『最優先』に使うべきだ。なぜ当たり前の使い道ができない?まずは日本人の生活を豊かにするところからスタートでしょうが。
この発言は「税金はまず日本人のために使うべきだ」という姿勢を鮮明にし、外国人への公的扶助を否定する内容となっている。
外国人への生活保護と法的背景
日本の生活保護制度は「国民」を対象に設計されている。しかし実務上は例外的に外国人にも支給されてきた歴史がある。1954年の厚生省通達によって、在留資格を持つ外国人については「人道的配慮」として生活保護を認める運用が始まった。現在も永住者や特別永住者、日本人配偶者や難民認定者などは対象となり得る。
一方で、2014年の最高裁判決では「外国人には生活保護法上の権利はない」と明言された。ただし同時に、行政裁量に基づく支給は認められる余地があるとされ、自治体による判断が続いている。このため法律と運用の間にずれが生じ、制度の曖昧さが議論の火種となっている。
政府と自治体の対応、相次ぐ裁判例
近年、外国人による生活保護申請を巡って裁判も増えている。千葉地裁はガーナ国籍男性の訴えを退け、「法律上は外国人を対象にしていない」と明確に判断した。一方で地方自治体は人道的観点から一定の支給を継続しており、現場では「制度と現実」の板挟みが続く。
厚生労働省は2025年7月、外国人優遇とのネット上の風説を否定した。厚労相は「支給世帯の増加は一部で誇張されている」と説明し、外国人による利用は全体の1%強にとどまることを示した。だがSNS上では「中国人ばかりが得をしている」といった誤解が拡散し、制度不信が根強い。
SNSの反応と社会の分断
へずまりゅう氏の投稿には支持と反発が相次いだ。
「困るなら母国へ帰ればいいという意見はその通りだと思う」
「日本人が納めた税金を日本人に優先するのは当然」
「人道を欠いた発想。共に暮らす外国人にも最低限のセーフティネットは必要」
「永住外国人や日本人の配偶者を一律に切り捨てるのは乱暴だ」
「デマに基づいた主張では信頼できない」
このように、ネット上の議論は二極化している。賛同者は「国民優先」を強調し、批判者は「人道」「共生」の視点を訴える。
今後求められる制度の明確化
へずまりゅう氏の主張は過激さが目立つが、背景には制度そのものの曖昧さがある。生活保護法が「国民」を前提としている一方で、行政は長年外国人に支給してきた。裁判所も一貫した基準を示せておらず、結果として自治体ごとに対応が異なる。
こうした状況を放置すれば、政治的対立や社会分断を深めるだけだ。今後は以下の取り組みが急務とされる。
1. 制度の法的整理
対象となる外国人の範囲や条件を明文化し、全国で統一した基準を作る必要がある。
2. 透明な情報発信
誤情報や偏見を防ぐため、政府や自治体は支給実態をわかりやすく公開し続けるべきだ。
3. 人道と共生の視点
税金の優先順位を議論しつつも、共に生活する外国人への最低限の保障をどう確保するか、国民的合意を形成していくことが求められる。
へずまりゅう氏の発言は、「国民優先」という素朴な感覚に訴える一方で、外国人支援をめぐる誤解や排除の感情を助長するリスクもはらんでいる。制度の矛盾を解消しなければ、この議論は今後も繰り返されるだろう。国民にとっても外国人にとっても、公平かつ透明性のある生活保護制度の在り方が改めて問われている。








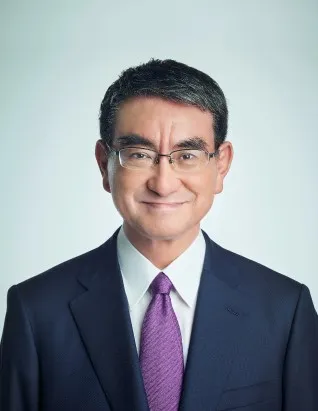
























![EBPM[エビデンス(証拠・根拠)に基づく政策立案]とは何か 令和の新たな政策形成](https://m.media-amazon.com/images/I/41y20VDvhnL._SY445_SX342_.jpg)
