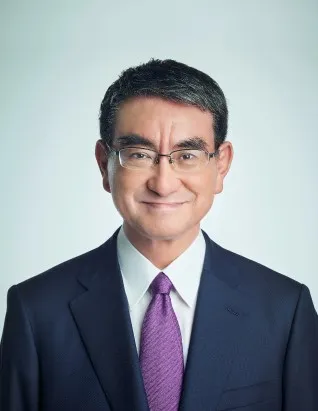2025-08-06 コメント投稿する ▼
【被爆80年の広島が問う核抑止の限界】湯崎知事「核なき安全保障こそ現実的な選択」
核抑止論の限界と広島からの問いかけ
広島は、被爆80年目の「原爆の日」を迎えた。平和記念公園で開かれた平和記念式典では、広島県の湯崎英彦知事が、核抑止論の脆さと核兵器廃絶の必要性を訴えるスピーチを行った。被爆地としての歩みと現代の国際情勢を重ね合わせ、改めて核のない安全保障のあり方を問いかけた。
知事は冒頭、原爆犠牲者への哀悼と被爆者・遺族へのお見舞いを述べ、戦後の広島の復興を振り返った。草木も生えぬと言われた街は、今や世界中から観光客が訪れる都市に変貌。しかし、その繁栄は世界の平和と安定があってこそだと強調した。
一方で、法と外交を基軸とする国際秩序は揺らぎ、「剥き出しの暴力」が支配する世界へと変わりつつあると警鐘を鳴らした。
抑止力は“絶対的な真理”ではない
湯崎知事は、核抑止を声高に唱える人々への疑問を提示した。確かに抑止の概念は戦争防止の一手段かもしれないが、それはあくまで人間が頭の中で作り上げたフィクションであり、万有引力の法則のような普遍的真理ではないと指摘。歴史上、ペロポネソス戦争以来、力の均衡による抑止は何度も破られてきたと語った。
特に、自信過剰な指導者の出現や民衆の高揚、誤解や錯誤によって、理性的な判断が働かず、抑止は簡単に崩れる可能性があると述べた。我が国が太平洋戦争開戦に至った過程も、その一例だという。
「核抑止は80年間守られたわけではない。破綻寸前の事例は複数あった」
「国を守っても山河が失われるなら、その抑止は無意味だ」
「核戦争が起きれば人類も地球も再生不能になる」
知事はこうした危機感を示し、核による安全保障は長期的には極めて危ういものであると訴えた。
核を除いた新しい安全保障構想
湯崎知事は、抑止力は軍事だけでなく外交や文化的影響力といったソフトパワーも含むべきだとし、その中から核という要素を外すべきだと主張した。
核抑止の維持には年間14兆円以上が投入されているとされ、その一部を核なき安全保障の構築に振り向けるべきだと提案。新たな安全保障の枠組みをつくるためには、資金だけでなく各国の英知と政治的意思が必要だと強調した。
ネット上でも、この発言には賛否が寄せられた。
「理想論だが、被爆地の知事が言わなければ誰が言うのか」
「核の傘なしで本当に国を守れるのか疑問だ」
「安全保障費の使い方を変えるべきという提案は現実的だ」
「軍拡競争を止めない限り、核廃絶は夢物語になる」
「未来世代のために、やる価値はある挑戦だ」
被爆者の言葉を胸に進む
スピーチの終盤、知事は被爆者であり、ノーベル平和賞受賞団体の活動家でもあるサーロー節子氏の言葉を引用。「諦めるな。押し続けろ。進み続けろ。光が見えるだろう。そこに向かって這っていけ」という力強いメッセージを紹介した。
知事は、この言葉は核兵器廃絶の道のりを象徴していると述べ、瓦礫の中で一筋の光を目指して進んだ被爆者の姿を重ね合わせた。そして「這い出せず命を奪われた多くの犠牲者の無念を晴らすためにも、私たちは粘り強く這い進まなければならない」と結んだ。
被爆地から発せられたこの訴えは、現実の安全保障の議論にどこまで影響を与えられるのか。世界が分断と対立を深める中で、広島の声がどれほど響くのかは、これからの国際政治の動向にかかっている。