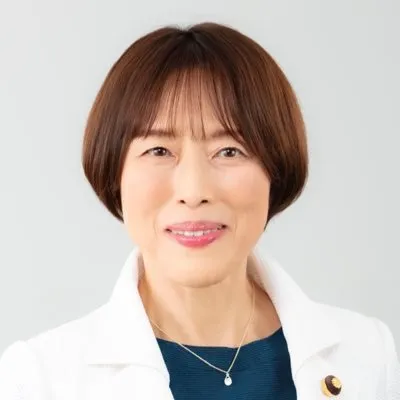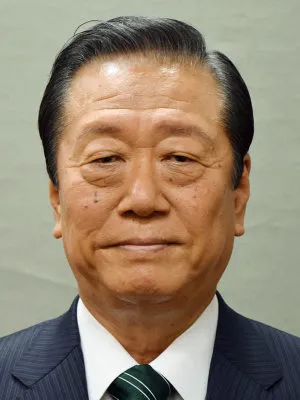2025-05-27 コメント投稿する ▼
子どもの安全確保へ文科省が緊急対応 スクールガード制度拡充と補助金活用を要請
今回の会議では、学校周辺の防犯対策を今一度見直すよう強く呼びかけたほか、元警察官などが防犯指導を行う「スクールガード・リーダー」の活用を推進する補助制度の紹介が行われた。 さらに、子どもたちを見守る地域ボランティアを支援する「スクールガード・リーダー」制度が紹介された。 例えば千葉県船橋市では、13人のリーダーが小中学校を巡回し、地域住民や教職員と連携して防犯活動を行っている。
全国で子どもの安全強化へ 文科省が緊急会議開催
子どもたちの下校中に起きる事件や事故が全国で相次ぐ中、文部科学省は5月27日、全国の教育委員会の担当者を対象に緊急の連絡会議をオンライン形式で開催した。今回の会議では、学校周辺の防犯対策を今一度見直すよう強く呼びかけたほか、元警察官などが防犯指導を行う「スクールガード・リーダー」の活用を推進する補助制度の紹介が行われた。
会議の背景には、大阪や埼玉、福岡などで5月中に発生した子どもが巻き込まれる事件や事故の多発がある。また、東京都立川市では、男2人が小学校に侵入して暴れる騒ぎも起きており、保護者の不安が急速に高まっている。これを受けて文科省は、安全確保に関する情報共有と具体策の確認を急いだ形だ。
現場任せにしない、安全体制の再構築
この会議では、教育機関に対し、危機管理マニュアルの改定や見直しを促すとともに、防犯カメラの設置や玄関のオートロック化に関する補助金制度についても説明された。学校単位の取り組みだけでは限界があるとの認識から、国の支援を受けながら地域全体で安全体制を再構築する必要性が強調された。
さらに、子どもたちを見守る地域ボランティアを支援する「スクールガード・リーダー」制度が紹介された。元警察官や教職員経験者など専門的知識を持つ人材が、防犯パトロールや危険箇所の助言、緊急時対応などで学校と連携し、子どもを守る取り組みを行う仕組みだ。
スクールガード・リーダー制度の役割と広がり
文部科学省は2005年度からこの制度を推進しており、現在では全国各地で導入が進んでいる。例えば千葉県船橋市では、13人のリーダーが小中学校を巡回し、地域住民や教職員と連携して防犯活動を行っている。彼らは月1回の研修も受け、最新の防犯知識や地域課題の共有に努めている。
制度にかかる費用は、国と地方自治体が共同で負担しており、実施主体である市町村が2/3、国が1/3を助成する形となっている。この財政的支援により、人的資源の確保が難しい自治体でも導入しやすい仕組みが整っている。
市民からも広がる安全対策への共感
今回の取り組みについて、ネット上でも多くの関心と賛同が寄せられている。とくにX(旧Twitter)やThreads、FacebookなどのSNSでは、以下のような声が見られる。
「地域で子どもを守る体制、大切。スクールガードもっと増やしてほしい。」
「不審者対応は学校だけじゃ無理。専門家の配置は安心につながる。」
「補助金制度、初めて知った。もっと広報して導入を促すべき。」
「カメラやロックも大事だけど、やっぱり見守る“人の目”が必要。」
「子どもたちの命を守る取り組みなら、税金の使い道として納得できる。」
子どもの安全を“社会全体の課題”として捉える時
学校にすべての責任を押し付けるのではなく、家庭、地域、行政がそれぞれの役割を果たす「協働」が今こそ求められている。とくに人口減少や地域社会の希薄化が進む中では、制度として安全網を整備することが一層重要となる。
今回の文科省の対応は、単なる現場任せからの脱却を意図したものだ。今後、こうした仕組みが各地に広まり、子どもたちが安心して通学できる社会づくりが進むことが期待される。