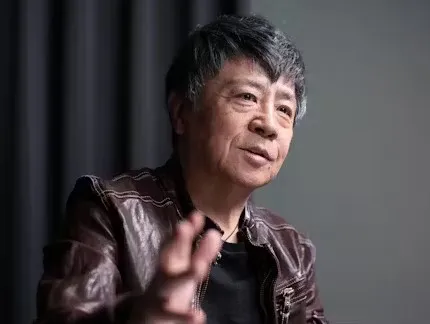2025-07-17 コメント投稿する ▼
日産追浜工場の生産終了に横浜市が危機感 山中市長が雇用と中小企業支援を要請
日産追浜工場の生産終了
横浜市長が危機感 地元企業と雇用への影響を懸念
追浜工場閉鎖の衝撃広がる
日産自動車が神奈川県横須賀市にある追浜工場での完成車の生産を打ち切ると発表した。これにより、地元のみならず広く横浜市にも波紋が広がっている。横浜市に本社を構える日産の決定に対し、山中竹春市長は17日、市役所でイバン・エスピノーサ社長と緊急面会を行い、「多くの企業や従業員に深刻な影響が出る」と強い懸念を示した。
横浜市ではすでに15日に対策本部会議を立ち上げ、特別経営相談窓口の設置を決定するなど対応を急いでいる。市内には日産と直接的あるいは間接的に取引関係を持つ企業が数多く存在し、部品供給や下請け、物流、整備など幅広い業種に影響が及ぶことは避けられない。
ネット上でも不安や怒りの声が噴出している。
「追浜工場閉鎖って、地域経済に大打撃じゃない?」
「日産の経営判断、地元に説明責任果たしてる?」
「雇用どうなるんだよ…転職も簡単じゃないのに」
「自治体はもっと早く危機察知できなかったのか」
「また企業の論理で地域が切り捨てられるのか」
日産の言い分と対応
エスピノーサ社長は「横浜市とも緊密に連携しながら、対応にあたる」と述べ、影響を受ける企業向けに説明会の実施を予定しているとした。しかし、工場閉鎖というインパクトの大きな決定を下した背景や、今後の従業員の処遇、地域経済への波及への対応については、まだ具体的な全容が示されていない。
追浜工場は長年にわたり日産の生産拠点として稼働しており、EV(電気自動車)の試験車両製造などで一定の役割を果たしてきた。しかし、世界的な生産再編や経営効率化の波を受け、今回の決定に至ったとみられる。
とはいえ、単なる「経営判断」では済まされない問題である。なぜなら、工場が立地することで形成された産業ネットワークや地元経済の循環、ひいては地域社会そのものが深く結びついていたからだ。
自治体の限界と責任
山中市長は「迅速な情報提供に努め、最大限の対策を取っていくべき」と強調する一方、日産という巨大企業の決定に自治体がどこまで影響を与えられるかには限界がある。実際、企業の海外移転や工場統廃合の決定は国の支援や規制の枠組みによって左右される部分も大きい。
今こそ地方自治体と企業、そして国が連携して、地域社会を守る仕組みを作る必要がある。雇用対策にしても、単なる転職支援や職業訓練だけでは意味がない。産業の空白地帯をどう埋めるのか、具体的なビジョンが求められている。
また、現行の法人税減税政策やグローバル資本主義のもとでは、こうした工場撤退は今後も各地で起こる可能性が高い。日本経済の基盤を支える「ものづくり」の現場が次々と姿を消す中で、政治の責任はますます重くなっている。
真に求められるのは減税と中小企業支援
こうした状況で最も必要なのは、迅速かつ的確な減税政策と中小企業への直接支援である。政府はこれまで「補助金」や「給付金」といった一時しのぎの対策を繰り返してきたが、今回のように構造的な雇用喪失が予見される場面ではまったく不十分だ。
とくに中小企業にとっては、雇用維持や設備投資のための資金繰り支援が急務だ。税負担を減らすことで資本を内部に蓄積させ、自助努力を後押しする政策こそが持続的な地域経済再生の鍵を握っている。
さらに、経済安全保障の観点からも、自国の製造基盤をむやみに縮小させるべきではない。海外生産に頼りすぎる構造を見直し、地域に根ざした経済の再構築を図るべきだ。
現場の声を真正面から受け止め、対策を「打つだけ」ではなく「効かせる」ための政治的リーダーシップが求められている。