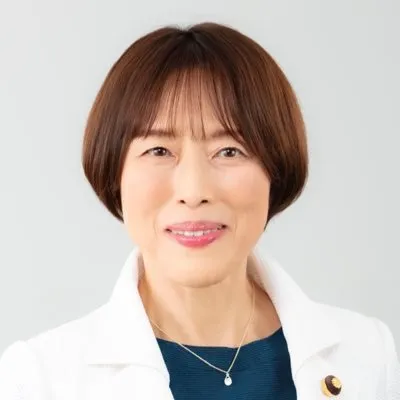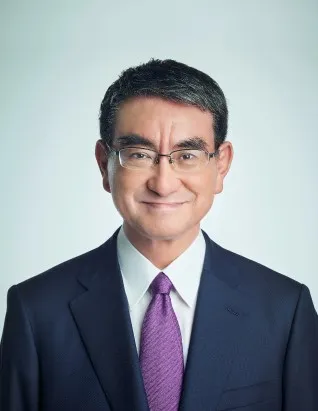2025-07-12 コメント投稿する ▼
「傍観者ではなく当事者に」…共産・吉良候補を応援する市民集会に違和感の声も 排外主義と差別を一括りにする“言葉の暴力”
共産党候補への“市民応援” 新宿駅前でスピーチ集会
7月12日夜、東京都新宿駅前にて「吉良さんを応援する人大集合」と題した街頭集会が開かれ、日本共産党の吉良よし子候補(現職)の再選を求めて市民有志らがスピーチを行った。
この集会では、外国人支援団体関係者、大学教授、音楽家などが登壇し、「差別と排外主義にNOを」「共産党の議席を減らしてはならない」といったメッセージが次々と飛び出した。
主催はJCPサポーターなど共産党支持層で構成されたグループで、司会を務めた中山ミユキ氏が開会を告げると、駅前の広場には数百人の聴衆が集まり、演説を聞き入った。
明治大学の鈴木賢教授は、「日本人ファーストを掲げる憲法案は法学的に論外。共産党の議席を減らしてはいけない」と主張。入管問題に取り組む活動家は「外国人が何かを奪っているというのはデマ」と訴え、音楽家のスガナミユウ氏は「マジョリティが変わらなければ社会は変わらない」と呼びかけた。
「なんで『日本人ファースト』が悪なの? 自国民を守って何がいけない」
「この人たち、排外主義と保守思想をわざと混同して攻撃してるよね」
「差別はよくないけど、日本の法律や文化を守るのも当然のこと」
「“マジョリティが変われ”って、選民意識の裏返しにしか聞こえない」
「日本の将来よりイデオロギー優先、共産党らしいわ」
SNSではこの集会に対して、共感と同時に強い違和感を覚えるという声も多く寄せられている。
「差別」と「秩序」を一括りにする危うさ
今回の集会では「排外主義と差別を許すな」「共産党の議席を守ろう」といった訴えが繰り返されたが、その言葉の裏側には“日本人としての当たり前の感覚”を異端視する姿勢が見え隠れしていた。
たとえば「外国人が何かを奪っているというのはデマ」と断じる声もあったが、現実には不法滞在や生活保護の過剰支給、治安問題など、無視できない課題が存在する。これを“デマ”と一括りにし、「異議を唱える側が悪」というレッテルを貼るやり方こそ、健全な議論を妨げる“言葉の暴力”に他ならない。
また、「マジョリティが変われ」という主張には、表向きの正義感とは裏腹に、日本社会の価値観や秩序を“時代遅れ”と切り捨てる傲慢さも垣間見える。民主主義とは、多数派・少数派のどちらかを否定する制度ではなく、相互の尊重にこそ価値がある。マイノリティを大義に多数派を攻撃する構図が、むしろ社会の分断を生んでいるという現実には、彼らは目を向けようとしない。
「傍観者でなく当事者に」…誰の“当事者”なのか
集会のテーマである「傍観者ではなく当事者に」という言葉自体は、政治参加の重要性を説くものとして理解はできる。しかし、その“当事者意識”が特定の政党や主張の代弁者になることを求めるのであれば、それは単なる“動員”でしかない。
本来の当事者意識とは、自らの生活、家族、地域、日本という国家の将来を真剣に考え、自分の頭で判断し、行動することを指すはずだ。そこには当然、「保守的な価値観」「国益重視」「文化・法秩序の尊重」といった選択肢も含まれる。
しかしこの集会では、それらをあたかも“差別”や“排外主義”として片付ける空気が支配していた。異なる意見や視点を封じ、都合の良い当事者意識だけを鼓舞する姿勢には、かえって民主主義をゆがめる危険性すらある。
選ぶのは市民の理性 「対立」ではなく「議論」を
共産党やその支持者が何を主張し、どのような政策を掲げようとも、それを否定することは民主主義において許されない。だが、同じように保守や現実路線、国益重視の立場もまた、正当な選択肢として尊重されるべきである。
政治を「差別か反差別か」という二元論に押し込め、保守的な考えを“悪”と決めつけてしまう風潮に、いまこそ警鐘を鳴らすべき時期ではないだろうか。私たちは今、冷静に考えなければならない。誰の言葉に説得力があるのか。誰が国民の暮らしと未来を本気で守ろうとしているのか。
本当の意味で「傍観者ではなく当事者になる」ためには、思想に酔うことではなく、現実と向き合う知性と責任こそが求められている。