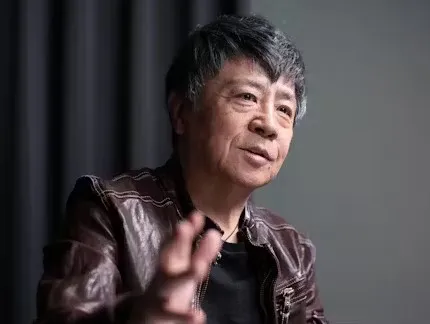2025-07-14 コメント投稿する ▼
玉木雄一郎氏が沖縄で訴えた「分断超える政治」 米軍基地と教育政策で示した“第3の選択肢”
保革二元論を超えて 玉木代表が語る沖縄の未来
国民民主党の玉木雄一郎代表が7月14日、那覇市で参院選と同日実施の那覇市議選に向けて応援演説を行い、「新しい政治スタイルを提案したい」と力強く訴えた。沖縄における長年の争点、米軍基地問題に触れながらも、単なる賛否やイデオロギーの対立ではなく、「実利と未来」を見据えた政治の必要性を強調した。
那覇市内の繁華街で行われた街頭演説には、買い物客や若い家族連れなど多くの市民が足を止めた。玉木氏はマイクを握り、「人づくりこそ国づくり。教育、科学技術分野にもっと予算を」と訴え、子育て支援や教育環境の充実を柱とする政策の必要性を強調。「未来の沖縄を形作るのは、米軍基地の是非だけではない」と語りかけた。
さらに、「沖縄の政治はどうしても『賛成か反対か』『保守か革新か』という二項対立になりやすいが、その枠に縛られたままでは何も変わらない。新しい選択肢が必要だ」と述べ、固定化した政治構図からの脱却を呼びかけた。
米軍基地問題には現実的対応を示唆
玉木氏が今回の応援演説でとくに配慮したのが、沖縄特有の課題である米軍基地問題だ。保革の立場を問わず、県民の生活や安全保障に直結する問題として長年議論が続いてきたが、選挙になると「基地賛成か反対か」の軸に話が集約される傾向が強い。
玉木氏はこの点に触れ、「基地の問題には、それぞれの地域、世代、立場で複雑な思いがある。そこに正面から向き合い、分断ではなく共存と共創の道を探るべきだ」と語った。
また、「沖縄の未来を決めるのは本土でも政府でもない。沖縄自身が考え、選び取るべきだ。そのために、私たちは対話をベースにした現実的な提案をしていく」と述べ、地方自治の尊重を強調した。
「基地の話ばかりじゃなく、子どもの教育とか生活の話をもっとしてほしい」
「玉木さんの『どっちでもない』という姿勢、ちょっと新鮮だった」
「反対派でも賛成派でもない立ち位置、むしろ安心感がある」
「沖縄のことを“票田”としてじゃなく、真剣に向き合ってくれてる感じがした」
「保守も革新もこりごり、新しい道を模索したい」
SNS上では、玉木氏の演説に対し、こうした共感の声が一定数見られた一方で、「結局、どっちつかずで責任を取らないポジションでは?」といった疑問の声も上がっている。
教育・科学技術への投資強調 経済基盤を見据える
玉木氏は応援演説の中で繰り返し「教育こそ国の土台である」と訴えた。大学や高専、職業訓練校への投資拡大を掲げるとともに、IT分野や観光、農業技術など沖縄が持つ可能性を伸ばすための支援策を提案した。
特に、観光偏重からの脱却と多様な産業育成の必要性に触れ、「観光業だけに頼る経済では不安定だ。地元の若者が地元に希望を持って働けるような、新しい産業構造を共に考えたい」と語った。
この点について、那覇市内の高校生の親からは「教育にもっと予算を、という話に初めて現実味を感じた」「受験や進学の話だけでなく、地元の雇用や将来に直結する話をしてくれてうれしい」といった反応も寄せられている。
“非対立型”政治の可能性はあるか
玉木雄一郎氏が今回訴えたのは、保守か革新か、賛成か反対かという構図を抜け出し、「課題にどう現実的に向き合うか」という視点だ。
こうした“非対立型”の政治スタイルは、沖縄だけでなく全国的にも政治不信の広がる中で一定のニーズを持つ。一方で、あいまいなスタンスや主張の弱さと捉えられれば、有権者に「決断力がない」と見なされるリスクもある。
とはいえ、米軍基地という極めて重いテーマを抱える沖縄だからこそ、対立を煽るのではなく、異なる立場をつなぐ“橋渡し”の役割を担える存在が求められているのかもしれない。
沖縄の選挙はいつも基地問題が中心に据えられがちだが、その背後には子育て、教育、雇用といった日々の生活に関わる切実な課題がある。玉木氏が提示する“第3の道”が、沖縄の有権者の心にどう響くかが、今後の選挙戦において注目される。