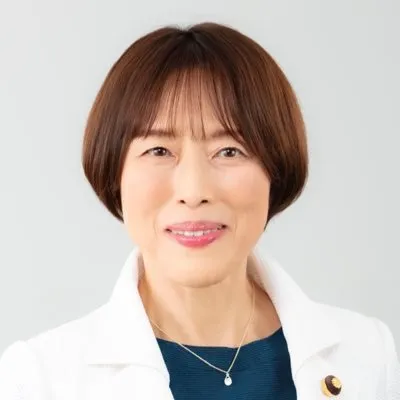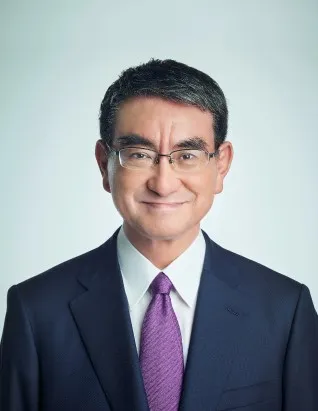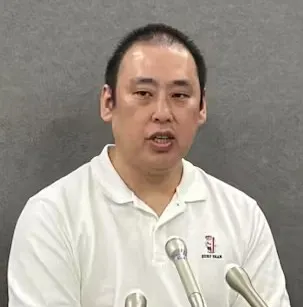2025-08-22 コメント投稿する ▼
能登地震被災者に医療費返納督促 5500人に1億超請求で波紋
能登地震被災者への医療費返納督促が波紋
2024年1月に発生した能登半島地震の被災者に対し、医療費自己負担を免除していた石川県後期高齢者医療広域連合が、免除要件を満たしていないとして「返納」を求める督促を出している。対象者は約5500人にのぼり、請求額は1億2700万円に達する。被災者の中にはすでに亡くなった人も含まれており、その場合は相続人が債務を背負う形になることが判明し、問題が広がっている。
「震災で苦しんだ人にさらに請求なんてあまりに酷い」
「役所の説明不足で免除を信じていたのに裏切られた気分」
「相続人にまで負担させるのは人道的にあり得ない」
「返納金より被災者生活の再建を優先すべき」
「国の制度設計が現場に責任を押し付けている」
免除制度の経緯と返納の根拠
厚生労働省は地震直後、医療費の支払いが困難な被災者に対し自己負担額を免除できるとの事務連絡を発出していた。対象は住宅の全半壊や生計維持者の死亡といった条件を満たす場合に限られたが、罹災証明が発行されるまでの間は、医療機関の窓口で患者が口頭で申告すれば免除できる仕組みが認められていた。
石川県では、その後の罹災証明や申請状況を確認したところ、要件を満たしていないケースがあると判断し、返納を求める通知を出したという。実際に督促状を受け取った高齢男性は、昨年3回の入院で免除された医療費約4万円を返すよう求められており、支払期限も明記されている。
自治体の対応と被災者の苦境
石川県後期高齢者医療広域連合の担当者は「納付期限を通常の2倍に設定するなど配慮している」と説明するが、実際に被災生活を送る高齢者にとっては負担が重い。生活再建すらままならない中での督促は「冷たい行政」との批判を招いている。
さらに担当者は「困窮している場合は自治体に救済を求めてほしい」と述べたが、制度上の責任を自治体に押し付けている印象も拭えない。こうした姿勢は、被災者への支援どころか心理的負担を増幅させているとの指摘がある。
過去の震災対応との比較
過去の大規模災害でも類似の事例は存在した。東日本大震災では岩手県が、免除を受けていた世帯が後に課税世帯となった場合に返納を求めたことがある。ただし宮城県では、保存年限が過ぎたため関連データを廃棄し、同様の対応を把握できない状況にある。
この比較から見えてくるのは、災害時の医療費免除制度が一貫性を欠いており、自治体ごとの判断や運用に左右されるという問題だ。国が制度を設計しながら、最終的な責任を現場に押し付けている点も批判の対象となっている。
制度のあり方と今後の課題
災害支援制度の目的は被災者の生活再建を支えることにある。しかし、今回の返納督促は「支援が逆に被災者を追い込む」事態を招いている。特に高齢者にとっては数万円の負担であっても重く、相続人にまで義務を課すやり方は社会的合意を得にくい。
政府と自治体は、返納督促という「冷たい支援」ではなく、免除の適用に関する透明性の確保と、生活困窮者に寄り添う運用を徹底すべきである。能登地震からの復興が進まぬ中で、制度の不備が被災者をさらに苦しめている現実は見過ごせない。