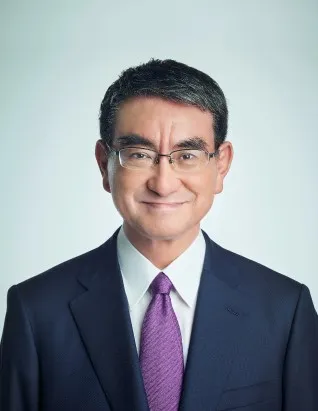2025-07-31 コメント投稿する ▼
立憲民主党、SNS戦略の強化求められる 参院選総括会議で地方組織が提言「無党派に届いていない」
地方組織からSNS対策を求める声相次ぐ
立憲民主党は7月31日、参院選の結果を踏まえた全国幹事長・選対責任者会議をオンラインで開催した。今回の参院選では、野党第1党として政権交代を視野に22議席からの増加を目指していたが、結果は現状維持にとどまり、地方組織からは厳しい声が寄せられた。
とりわけ目立ったのは、無党派層へのアプローチの弱さだ。地方幹部からは、「SNSの発信力が他党に比べて圧倒的に劣っている」「若年層や都市部の有権者に届いていない」といった意見が続出。参政党や国民民主党が積極的なSNS活用で支持を広げた事例を引き合いに、立民も戦略転換を迫られている。
野田代表「惰性だった」…無党派層との距離を痛感
会議の冒頭、野田佳彦代表は「今回の結果は厳しく受け止め、しっかり総括して次に備えたい」と語り、今後の組織改革と戦術の見直しに意欲を示した。
さらに、「これまでは野党第1党というだけで無党派層が流れてきたが、今回はそれに甘えていた」とも述べ、「メッセージの伝え方に大きな改善の余地がある」と反省を表明。時代の変化に応じた情報発信の在り方を見直す必要があると自認した。
この発言には、今の立憲民主党が「批判型政党」としての性質から脱却しきれていないという内部の認識もにじむ。
執行部への責任論は出ず 一本化には一定の評価も
大串博志代表代行によれば、今回の会議では執行部の責任を問う声は上がらなかったという。一方で、1人区での候補者一本化を評価する意見は多く、「野党間での調整には成果があった」と一定の手応えもあったようだ。
とはいえ、一本化に成功してもなお結果が伸びなかった現実は、個々の候補の地力や党の魅力が他党に比べて弱かったことを示している。ネット空間における立民の発信力のなさは、致命的な選挙戦略の欠陥として再認識されている。
有権者からも「SNS弱すぎ」「誰に届いてるの?」の声
市民や有権者の間でも、立憲民主党の情報発信に関する課題は以前から指摘されてきた。参院選後のSNS上でも、次のような声が多く見られる。
「立憲のSNS、正直全然印象に残らない」
「どの世代に向けて発信してるのか見えない」
「候補者の名前も政策も出てこないんだよね」
「批判ばかりで、自分たちのビジョンが伝わってこない」
「国民民主や参政党のほうがずっと戦略的に動いてる」
こうした声は、立民が支持を広げるべき無党派層、特に若年層からの評価が低下している現実を浮き彫りにしている。
SNS戦略の転換こそが党再生の第一歩
いまや選挙戦において、SNSは単なる「広報」ではなく、有権者との「対話の場」として機能している。限られた紙のチラシや街頭演説だけでなく、X(旧Twitter)やYouTube、TikTokなど、若者の情報接触の主要経路に踏み込めなければ、支持拡大は難しい。
立民が今後政権交代を本気で目指すのであれば、時代に適応した情報戦略と候補者育成、そしてなにより明確なメッセージの構築が不可欠だ。
旧民主党時代からの「批判型野党」のイメージを払拭し、対案をもって信頼を取り戻すには、デジタル時代における新しい政治スタイルへの転換が求められている。